| 一輪庵HOME 創作TOP |
感想などは掲示板 またはメールでどうぞ |
| 『楽園』さんに登録しました。 「らら美」などで検索すると、拙作に投票できます。 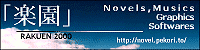 |
|
Velvet Gold 〜天鵞絨黄金〜 (『楽園の灰』シリーズ)
根源の森 1
| 涼やかな夜風に、香の薫りと清めの鈴の音が混じる。 人々は息を潜めて、郷市の北西に位置する聖カウサルの山を見上げる。 光のビーズが山道を示し、一際明るく浮かび上がる山頂の祭殿からは、真夜中になっても歌声が途絶えることはない。 遠い旋律と緻密な拍節[ウスール]が王の宮処[みやこ]を包み、歌聖楽都[カンターリア]の呪法が張り巡らされてゆく。 人々は祭りの熱気とともに、目に見えぬ霊的な大波が近付いてくるのを、魂の奥深くで感じていた。 聖カウサルの祭殿は、緑園郷[グリアーナ]を拓いた初代の航海王タールート以来、代々の王たちが即位し、年ごとに花鎮めを行ってきた聖所だ。 祭殿では、数十人の楽師たちがそれぞれの仕事に立ち働きながら、絶え間なく賛歌を紡ぎ続けていた。 始まりも終わりもなく繰り返す旋律が寄せては返し、しだいに無秩序な雑音を呑み込んでいく。 石畳を踏む足音も、祭殿を掃く箒の音も、樹々の葉を揺らす風さえもが、一つの大きな歌となってカウサル山を包んだ。 山はゆっくりと聖化され──むしろ聖なる本質をついに顕し──下界とは違う時の歩みを始める。 そうしてカウサルの山は呪的な結界を張り巡らされ、物質的な構造以上の意味と力を宿す場となっていった。 満月が西の空に傾く深夜に至り、ディハーナはカウサル山を登って祭殿に向かった。 不思議な音律に包まれた参道を進むにつれ、ディハーナは高く登りながら、不思議とどこか深い水底へと降りてゆくような気がしていた。 聖楽師[アンヘル]の金位は、祭殿の最奥、壁も屋根もなく柱にだけ囲まれた祭域の、幕屋の中で新王を待っていた。 その幕屋へと続く白い石畳を、点々と蝋燭の炎が照らしていた。 ここまでともに来た諸候や楽房の主座、女官たちを残し、ディハーナは一人、古びた石柱の間を抜けて祭域に足を踏み入れた。 幕屋の向こう、柱の間では、間近に迫る樹々の影が揺れていた。 ディハーナは幕屋の入口に掛けられた真っ白な薄布を、そっと両手で左右に押し開けた。 足もとに一つだけ燈火を灯し、純白の聖衣に身を包んだ聖楽師の金位が座っていた。 金位はディハーナを見て静かに立ち上がると、無言で王を結界内に招き入れた。 手首に巻いた連鈴が、幽かに透明な音色を響かせた。 揺れる燈火が淡い光輪を投げ掛け、二人はその中で、向かい合って腰を下ろした。 銀の香炉から深い森の薫りが立ち昇っていた。 人々の気配が遠ざかり、ただ遠くから響く歌声と、鈴や笛、何種類かの弦楽器と打楽器の静かな音だけが細波のように寄せてくるだけだった。 ディハーナは聖楽師の金位を見つめたが、その姿は今にも揺らいで向こう側が透けて見えるような気がした。 確かにそこにいるはずなのに、彼が本当にいるのは此処ではない何処かだと思えてならない。 色の薄い不思議な瞳と見つめ合っていてさえ、目をそらしたら最後つぎの瞬間にはもう、この少年の貌形を思い出せないのではないかとディハーナは思った。 ふと、楽房の主座の言葉が思い出された。 ――聖楽師[アンヘル]の歌というのは、心には残っても記憶には残らないのです。一夜の祭礼で聖楽師の歌を聞いた人々は、それがどんな歌だったかを、思い出すことはないでしょう。ただ素晴らしい一夜を過ごしたということ以外、人々の記憶に残ることはありません。呪歌とはそういうものです。本当の魔法は、目に見えない魔法なのですから…… ならば……とディハーナは思った。 ならば、金位は存在自体が魔法なのだ。 彼自身が聖都の歌そのものなのだ。 金色の髪をした少年が、銀の香炉を掲げて目を閉じ、そっとハミングで旋律を紡ぎ始めた。 覚めてみる夢だ……と、ディハーナは思った。 世界の地平が飴細工のように曲がり、遠く、深く、ディハーナは運ばれてゆく。 風が吹き抜けていった。 頬を毛先がくすぐる。 顔を上げたディハーナは、木漏れ日の中で立ち尽くしていた。 どこまでも続く深い森だ。 広々と枝を伸ばす樹々が、空高くでその枝先を触れ合わせている。 露を含んだ下草が、厚い絨毯のように地面を覆っている。 ゆっくりと流れていく薄もやの中、光の柱が樹冠から伸びていた。 その中に、聖楽師の金位が佇んでいた。 ディハーナは彼を見て呟いた。 「ここは……?」 「……緑園郷の森です」 「こんなに美しい森があったのか……」 少年は静かな微笑を浮かべた。 「ここはあなたの心の森であり、また緑園郷の魂の森でもあります。森の根源の森なのです」 ディハーナは少し戸惑ったようにもう一度辺りを見回し、微かな落胆を滲ませて呟いた。 「現実の世界じゃ、ないのか……?」 「現実の別の層です。言ったでしょう? 根源の森だと」 少年はゆっくりと歩きだした。 その後について行きながら、ディハーナが訊ねる。 「どこへ向かってるんだ?」 「森の奥へ。あるいは中心へ」 「そこで……何を?」 「あなたを王にする〈聖樹〉があります。あなたは聖樹に至るため、妨げるものを倒し、手に入れるべきしるしを持ち帰らねばなりません」 「しるし、って……?」 小柄な金位はディハーナを見上げ、小さく首を傾げた。 「私にもわかりません。あなたが見つけるのですよ。王になるのは、あなたなんですから」 ディハーナは足もとの草を踏みしめながら、胸の高鳴りを感じていた。 「代々の王たちも皆、ここを通っていったのか?」 「……体と意識を持ったままこの森に至る者は多くありません。大概は、夢うつつの中でこの森の影を垣間見るだけです。多分、あなたはこの國の大地と、より深く結びつけられる運命を持っているのでしょう」 ディハーナは軽く笑って首を振った。 「まさか……俺は王になんかなるはずじゃなかった。尊い方[マフディー]、これは金位の異能だろう?」 少年は静かに微笑んだ。 「それだけじゃありません……金位なんて、人が思うほどたいしたものじゃない」 その口振りが意外なほど大人びて感じられたので、ディハーナは隣を行く少年に思わず目を向けた。 まだ子供のようだと思っていた微笑が、なぜか知らず年老いて見えた。 「あっ……!」 すると急に、木漏れ日の中で少年の輪郭が揺らいだ。 と、思う間もなく、少年の体が透けて向こう側の樹々が見えてきた。 ディハーナは咄嗟に手を伸ばし、金位の腕を捕らえようとした。 だが二人の間を一陣の風が吹き抜け、ディハーナの指先は空を切るだけだった。 「おい、置いてきぼりかよ!」 少年の姿を探して周囲を見回すディハーナの耳に、どこからとも知れず声だけが響く。 「私が案内できるのはここまでのようです。ここから先は、王よ、あなた自身の力で」 「そんなこと言っても、どっちに行きゃいいのかも分からねぇぞ」 「聖樹へ……」 遠い木霊を残して声は途切れ、ディハーナは森の中に一人残された。 「……ちくしょう、結局置いてきやがった」 ディハーナは仕方なさそうに辺りを見回した。 樹々の梢の高みに鳥たちが通い、枝葉の風さやぎに混じって鳴き声が響く。 風が強くなっていた。 ふと、生い茂る枝葉を抜けて、〈風の道〉が見えた気がした。 背中を押す風が伸びた髪をなぶり、ディハーナの頬に笑みが浮かんだ。 ディハーナは風の道のその先を見つめ、歩き始めた。 足取りは軽かった。 |
| 一輪庵HOME 創作TOP |
感想などは掲示板 またはメールでどうぞ |
| 『楽園』さんに登録しました。 「らら美」などで検索すると、拙作に投票できます。 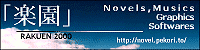 |
|