| 一輪庵HOME 創作TOP |
感想などは掲示板でどうぞ |
| 『楽園』さんに登録しました。 「らら美」などで検索すると、拙作に投票できます。 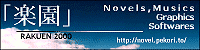 |
|
楽園の灰 第1話
じゅかいのとりこ
1.
呪楽師だったお婆が最前の音に還ってから、村の様子が変だ。
どこかが、何かが、狂ってしまった。
そして五日目、とうとう──
| 命は……非存在の海に浮かぶ、存在の岸辺だ──と、お婆は言っていた。 アルモナはよく覚えている。 偏屈で気難しいお婆が、その時だけとても敬虔な横顔を見せていた。 お婆は言っていた。 すべては最前の音[いやさきのね]からはじまり、最前の音に還る。 だからそれは、最果ての音[いやはてのね]でもあるんだ、と……。 そのお婆も最前の音に還った。 それ以来、レピ村の様子が、どうもおかしいのだ。 「放ってみな」 農夫がぶっきらぼうに言った。 アルモナは、一掴みの木イチゴを手に、首を傾げる。 「放る……? 食べ物を粗末にしちゃいけないってお婆が……」 「いいから、橋の向こう目掛けて放ってみな」 アルモナは眉根を寄せ、川面と橋を、そして橋の向こうに続く一本道を見やった。 石橋の小さなアーチ型の橋脚が、午後の日を浴びて川面に影を映している。 もう一度、農夫の顔を見てから、アルモナは小さな赤い実を一つ抓んで、勢いよく放り投げた。 すると、向こう側に木イチゴが落ちる音がするかわりに、アルモナのおでこにコツンとぶつかる物があった。 足もとに落ちたのを見れば、投げたはずの木イチゴだった。 「なにこれ?」 アルモナは眉を顰めて木イチゴを拾い上げた。 木イチゴを跳ね返すような障害物は、何もない。 しっかりした石橋の向こうは、すぐ先の上り坂まで道が続いているのが見える。 さらに目を凝らせば、大きくカーヴしながら木立の中へ消えてゆくずっと向こうまで、道は続いている。 「な?」 農夫は溜息混じりに、橋の向こうを見やった。 アルモナはもう一度、今度はもっと遠くへと、木イチゴを投げてみた。 ヒュッと、耳元をかすめて、木イチゴは彼女の後ろに落ちる。 わけが分からずに口をパクパクさせながら、アルモナは農夫を見た。 「……戻って来ちまうんだなぁ」 その口調が妙にのんびりしていたせいで、アルモナは余計にあたふたしてしまった。 意味もなく向こう岸と自分の足もとを指さしたり、くるくると辺りを見回したあと、ドスンと片足で地面を踏んだ。 「んもうっ! どうなってんのよ!」 二人が立っているのは、街道へと続くルミリエ川の橋だった。 とにかく来てみろと、農夫がアルモナを引っ張って来たのだ。 「人は……? 渡れるの?」 「……行ってみな」 アルモナは勝ち気そうな眉をキッとつり上げ、勢いよく橋を渡り始めた。 真っ直ぐに前を見て、一歩ごとに足を踏みしめる。 そして……橋の終わりでちょっとためらってから、思い切って向こう岸へと一歩をおろした、つもりだった。 しかしいつの間にか、目の前には農夫がぬっと立っていた。 アルモナはもとの場所へと戻ってきてしまったのだ。 「なんでー?」 アルモナはくるりと向きを変えると、今度は思い切り走って向こう岸を目指した。 しかし、結果は同じだ。 農夫の横を通り過ぎて、アルモナは慌てて止まる。 アルモナは橋に背を向けたまま、わなわなと肩を震わせた。 「この橋、渡れない……!?」 「どうやら、なぁ……」 農夫も彼女の隣に来て腕を組み、長々と溜息をついた。 とうとうここまで来たか、とアルモナは思った。 村の呪楽師だったお婆が最前の音に還ってから、村は異変続きだったのだ。 ──なんで、こう次から次へと問題が起こるのよ…… アルモナはきゅっと唇を結び、鼻の真ん中にある横一文字の傷痕を指先でなぞった。 村の楽師という肩書きが、アルモナの背にのしかかる。 お婆亡きあと、村の呪楽師はアルモナなのだ。とりあえず。 彼女はお婆の最後の弟子だ。 他の弟子たちは何十年も前に独立してどこかへ行ってしまっている。 最初の頃の弟子の何人かは、すでにお婆より先に最前の音に還っていることだろう。 他に誰もいないのだから仕方ない。 まだ十七とはいえ、成り行き上、当面はアルモナが村の呪楽師の役割を引き受けるほかない。 勝ち気そうな眉の間に皺を寄せ、くるくると表情豊かな瞳も、ここ数日は悩みに曇りがちだった。 誰もが認める半人前ではあったが、アルモナは体力と根性を頼りにがんばってきた。 同年代の少女たちに比べると、アルモナはだいぶ大柄な方で、肩幅は広く腕力も強い。 力仕事なら得意だが、楽器の腕の方は、まだまだ……。 落ち込みそうになると、きゅっと口を結び、鼻のところの刀傷の跡を、指先でなぞる。 いつの間にかそれが癖になっていた。 とにかく、日に焼けた肌に、慣れない白い裾長の楽師服を着込み、髪は垂らした方が楽師らしいとは思いつつも、邪魔なのでこれまで通り後ろで一つに編んで村中を走り回ってきたのだ。 しかし…… ──どうすればいいってのよ? あたし、何もできないのに……お婆はもういないのに……! なんとかしなきゃ、と、そればかり頭の中で繰り返すが、何をすればいいのか見当もつかない。 木イチゴを握りしめて肩を震わせるアルモナを、農夫がのぞき込んだ。 「困ったよなぁ……せっかく都に、木イチゴ売りに行こうと思ったんだが……」 さして困っているとは思えない農夫の口振りに、アルモナの焦りがぷっつりと切れた。 彼女はやけくそになって、振り向きざま、手にしていた木イチゴの残りを橋の向こうへと放り投げた。 5、6粒はあったはずだ。 しかし、アルモナのところへ戻ってきたのは、たった一粒だった。 「うわー、木イチゴだぁ!」 橋の上で、声がした。 「うっれしいなぁ!」 若い男だ。 楽師の白い裾長を着ている。 両手に受け止めた木イチゴを、ニコニコして数えながら、その青年は橋を渡ってくる。 彼の足首に巻かれた飾り輪[カルカール]の連鈴が、シャラシャラと涼しげな音を響かせていた。 アルモナも農夫も、たった今まで、そんな音にさえ気付いていなかった。 ちょうど坂道の向こうで、姿は隠れていたのだろう。 まるで何ごともないかのように橋を渡りきると、青年はアルモナたちの前で止まった。 「お久しぶり、ヤハディさん。アルモナ、これ食べてもいいの?」 名前を呼ばれたが、アルモナも農夫も、彼に見覚えがなかった。 ぼさぼさの伸びっぱなしの髪は、陽射しに色褪せてトウキビのヒゲのようだ。 もともと薄い髭を数日ほったらかしにしたのだろう、無精ひげがひどく情けない具合に伸びている。 小柄な体を埃っぽい裾長に包み、風除け布[ブルクー]を畳んで肩に掛け、首からは魔よけの飾り紐を何本かたらしている。 見るからに長い(貧乏な)旅暮らしが偲ばれる。 アルモナは呆気にとられて青年を見ていた。 目の前でニコニコしている小柄な青年は、アルモナと視線の高さがほとんど変わらない。 透けるような、不思議な瞳の色だけが、妙に印象的だった。淡い淡い、藤色の瞳…… ハッと我に返ったアルモナは、ちらりとヤハディに視線を送り、囁いた。 「この人……誰だっけ?」 「えーっと……」 青年は二人を見て、にこりと笑った。 「やだなぁ、リーアですよ。二人とも、春の陽気でモーロクしちゃったの?」 木イチゴを一粒口に放り込み、青年は呑気に続けた。 「お婆のとこで、ちょくちょく世話になってたでしょ? 離れに居候させてもらって……」 言われてみれば、旅の楽師がときどき転がり込んで来ては、離れで居候を決め込んでいたような気が……しないでもない。 いや、確かにそういうのがいた……ような気がする。 アルモナもヤハディも、定かには思い出せないながらも、何となく納得した。 「ホントにどうしちゃったの? 物忘れでもはやってるんですか?」 アルモナはハッとした。 「楽師、だったよねっ」 リーアと名乗った青年は、きょとんとして裾長の服を抓んだ。 「御覧の通り」 アルモナはその姿を見て、ちょっと首を傾げた。 「楽器も持ってないようだけど……?」 そう言われて、リーアは慌てて辺りをきょろきょろと見回し、何かを見つけて道端に走った。 アルモナの前に戻ってくると、リーアはにっこり笑い、道端でもぎ取ってきた金糸笹の一葉に、指先で器用に切れ目を入れ、唇に寄せた。 笹笛の澄んだ音色が、短い旋律を響かせる。 アルモナは呆れて溜息をついた。 「食い詰めて楽器まで売っちゃったのね……」 それでも、音色はきれいだし音階も正確だ。 ま、いいわ……と思い、アルモナはリーアの肩を、両手でがしっと掴んだ。 「物忘れで失せ物で橋が渡れなくて大変なの! 一人じゃどうにもならなくても、二人なら何とかなるかも知れないわ! リーア……力を合わせて、この村を救いましょう!」 |
| 一輪庵HOME 創作TOP |
感想などは掲示板でどうぞ |
| 『楽園』さんに登録しました。 「らら美」などで検索すると、拙作に投票できます。 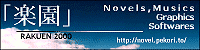 |
|