| 灰色のビルの窓枠に腰掛けて、ゴン之助は金色の瞳で不思議そうに通りを眺めていました。 一年の終わりのこの季節、街をゆくニンゲンたちはなんだかせかせかと忙しなく、急ぎ足で通り過ぎてゆきます。 行き交う人間達の向こうには、それよりももっとすごいスピードで走り過ぎて行く自動車が、ぎんぎん光りながら流れております。 (昔はこの辺りも、ずっと静かなところだったんだがなぁ) ネズミよりも人間の方が多いこの街で、ゴン之助はずっと長いこと暮らしてきました。 金茶色の毛並みは寄る年波のせいで薄くなりがちでしたが、まだまだ足腰は丈夫です。 (それにしても、何だってニンゲン達はこんなに急いで歩くんだろう…) 通りを歩く人間の幾人かが、ゴン之助が座っている窓枠の建物に入ってゆきました。 古めかしい石造りの、重たそうなビルディングです。 ゴン之助はくるりと首を回して、窓の中を覗きました。 黒く濡れた鼻が微かにヒクヒクと動き、真っすぐに伸びたヒゲがぴくぴくとふるえます。 (何だ…?) ゴン之助は、しきりに首を傾げました。 中には大勢のニンゲンがいて、そこは何かのお店のようです。 長ーい机のあちら側とこちら側で、ニンゲン達がさかんに何かを交換しているのです。 (…何をやってるんだ?食べ物を買ってるんでもなし、他の品物でもないようだし…) ニンゲン達がやり取りしているのは、どう見てもただの紙切れなのです。 「あれはな、お金だよ」 すぐ耳もとで声がして、ゴン之助はびっくりして窓枠から飛び降りました。 「や、失礼、驚かせてしまったようだね」 そこには、背広をきちんと着込んだお爺さんが立っていました。 白い口髭をたくわえ、片手にステッキを握り、頭の上には茶色のソフト帽を乗せて、にこにこと笑っています。 ゴン之助はお爺さんを見上げ、それから周りをキョロキョロと見回しました。 そしてふふんと鼻で笑うと、もう一度お爺さんを見つめました。 「……あんた、幽霊だね」 お爺さんは片手でちょっと帽子を持ち上げて見せました。 「賢い猫じゃのぉ。どうして分かった?」 ゴン之助は、莫迦にするなとでも言いたそうに胸をピンとそらせます。 「だてにこの街で長く生きてきたわけじゃない。そのくらい分かるさ。他のニンゲンに見えなくて、猫にだけ見えるのは、幽霊だ」 「なるほど」 おじいさんは感心したように頷いて、口髭を指先で撫でました。 「ところで猫よ、君の名は?」 「ゴン之助だ」 「ゴン之助か。いい名じゃ」 ゴン之助も前足でヒゲを撫でながら訊き返します。 「幽霊、あんたは?」 「ふむ……頭取と呼んでくれたまえ」 「トードリか。幽霊にしちゃ、いい名前だな」 二人はそれぞれヒゲを撫でながら、顔を見合わせてニヤリと笑いました。 「……して、ゴン之助や、さっきからこの窓の中を覗いておったが、お前は銀行に興味があるのかね?」 「ギンコウ?この建物は、ギンコウというのか?」 ゴン之助はぴょんと窓の縁にのぼって、もう一度窓の中を覗き込みました。 「ニンゲン達は、この中で何をやっているんだ?」 幽霊のトードリも、ゴン之助の隣で窓の中を覗き込みます。 「お金を預けたり、預けた分を返してもらったりしているんだ」 オカネなら、ゴン之助にもちょっとは分かります。 それを払わずに店先の魚なんかを失敬すると「この泥棒猫!」と店の人が追っかけてくるのです。 「オカネを…預ける…? なぜ?」 「いつも大金を持ち歩くわけにはいかんじゃろう?落としたり、盗られたりするかも知れない」 「つまり…魚の頭を木の根本に埋めておくようなもんか?」 「まあ、そうじゃな」 トードリはステッキに両手を預けて、にこにこしながら銀行を覗いています。 「それに、銀行にお金を預けると、ちょっとだけじゃが、お金がだんだん増えていくんだ」 「どうして?」 ゴン之助はくるりと首を傾げてトードリを見上げました。 「銀行は、預かったお金を他の人に貸してあげる。その人は返すとき、借りた分より余計にお金を返すんじゃ」 「余計に?どうして借りた分だけ返すんじゃいけないんだ?」 「ふむ、利子といってな…」 トードリは鼻の頭を、ちょっと指先で掻きました。 「そもそもの利子の起源はこうじゃ。昔の人間達は、その年に最初に刈り入れた稲穂や、最初に採れた作物、最初に揚がった魚なんかは、神への捧げ物にして、蔵に納めたんじゃ。特に米の場合、秋に初穂を奉納して、翌年の春には、それを種籾にするために借り受けて、秋にはまた、借り受けた分より少し余計に、稲穂を蔵に返す。今年も無事収穫できましたと、感謝を込めてな。つまり……利子っていうのは、もともとはありがとうの気持ちみたいなもんなんじゃ」 ゴン之助の頭の中に、懐かしい田圃の風景が浮かんできました。 昔はこのあたりだって、ちょっと遠出をすれば田圃が広がっていたのです。 そして秋祭りの太鼓の音、ピカピカ光る色電球、トウモロコシの焼ける匂いや、ソースの焦げる匂い……。 そんな懐かしい風景の中を、ホンワリと輝くたくさんのありがとうの気持ちが行ったり来たりする様子を、ゴン之助は想像しました。 「……ありがとうの、気持ちか…」 ゴン之助は、なんだかとても感心してしまいました。 魚の頭を一つ、神さまにありがとうと言いながら他の猫に貸してやったら、忘れた頃に、その猫が「この間はどうもありがとう」と言って、魚の頭を一コと半分、持って来てくれる…! 公園の木の下に隠しておくのより、ずっとずっとステキだ、とゴン之助は思いました。 「……つまり銀行は、神さまへの捧げ物を納めていた蔵の代わりをしているんだな?だから『気持ち』を預けると、『気持ち』が余計に増えるってわけか…」 トードリは嬉しそうに何度も何度も頷きました。 「お金はただの紙切れに見えるが、いろんな気持ちを乗せ、想いを乗せて、人々の間を巡って行くんじゃよ。ありがとうの気持ち、ご苦労様の気持ち、おめでとうの気持ち、お大事にの気持ち、よろしくの気持ち…。お金とはそもそも、そういう『気持ち』そのものなんじゃ」 ゴン之助の金色の瞳がきらきらと輝きました。 「人間もなかなかやるじゃないか。ギンコウとはずいぶんステキなものだな」 ゴン之助は道行く人々に目を向けました。 この人たち一人一人が、ポケットにいくらかずつ、そんな『気持ち』を持って歩いているのかと思うと、なんだか街中がきらきら輝いて見えてくるのです。 実際、ゴン之助の金色の目には、通り過ぎて行く人々のポケットやバッグの中で一つ一つの『気持ち』たちが、それぞれの色で輝くのが見えるのです。 うっとりと街を眺めるゴン之助の向こうで、銀行のシャッターが閉まり始めました。 「今日は、銀行はもうお終いじゃ」 銀行の玄関からは次々と人が出てきます。 西の空にはどかどかと雲がかかり、その間からずうっと斜めに、お日さまのよわい光がこの街に注いでいます。 自動車の列や忙しげな人間達は、みんな仄赤く照らされながら流れております。 ゴン之助とトードリは、ずいぶん長い間、街行く人や、自動車の流れをぼんやりと眺めておりました。 ふと、湿った風を感じて、ゴン之助はトードリの方を振り返りました。 「どうした、トードリ。何が哀しい?」 トードリは静かに、銀行の玄関の方へ歩いてゆき、広い階段のすみっこに腰を下ろしました。 ゴン之助もすぐにその隣に座ります。 警備員はもういなくなっておりますので、ゴン之助も追い払われずに済みました。 「ワシは、銀行を愛しとる」 トードリは噛みしめるように呟きました。 「しかし人間はすぐに、お金に込められた大切な『気持ち』を、忘れてしまう」 「なぜ忘れる?忘れないために、オカネがあるんじゃないのか?」 トードリは遠い眼差しで、ビルの隙間に見える夕焼けを眺めました。 「確かに、見えない気持ちを見えるようにするために、お金は生まれたのかも知れない。だが、そんな気持ちを人間たちが忘れてしまったらどうなる?気持ちのこもらない、ただの紙切れになっても、カネはカネじゃ。人間には区別が付かない。気持ちはお金に閉じこめられたまま、輝きを失う」 「オカネが気持ちを閉じこめるなんてことがあるのか?」 ゴン之助はびっくりして訊ねました。トードリは口をヘの字に曲げます。 「うむ。刈り入れた初穂を捧げるような『ありがとうの気持ち』を、人間達はいつの間にか忘れてしまった。今では、銀行に集められたお金は、意味のない数字になって世界中を駆け巡り、ただ数字を増やそうとするばかりだ。増えるのは数字じゃない、気持ちなんだ。なのにお金に込められていたはずの気持ちは輝きを失い、取り残され、薄められ…そしてお金の中に閉じこめられてしまうんじゃ」 「…でも、『気持ち』がこもってなきゃ、お金はあんなにきれいな光を出さないだろう?」 トードリは哀しげにゴン之助を見つめました。 「君たち猫族なら『気持ち』の光が見えるんだが、人間にはそれが見えないんじゃよ。ちょうど、普通の人間達に、幽霊であるこのワシが見えんようにな…」 急ぎ足で通り過ぎてゆく人々の誰一人、ここに座っているトードリに目を留める者はありません。 みんなせっせと人をかき分けながら行き過ぎるだけです。 ゴン之助は銀行の奥で、オカネと一緒に閉じこめられ、取り残された『気持ち』たちが、輝きをなくして寂しそうにふるえている様子を想像しました。 (『気持ち』を置き去りにしたら、それはもうオカネじゃない。飼い主が猫を置き去りにしたら、その飼い主はもう「ただの人間」になって、「猫と暮らしてる人間」ではなくなってしまうのと同じだ。オカネだって、『気持ち』を置き去りにしたら、ただの紙切れだ) ゴン之助は勢いよく立ち上がり、トードリを真っ正面から見上げました。 「トードリ、『気持ち』たちを助けに行こう!」 「な、何じゃと?」 ゴン之助は長い尻尾を真っすぐにピンと立てて、トードリに言います。 「オカネに閉じこめられて、人間達に置き去りにされた、大切な『気持ち』たちを助けに行くんだ!」 トードリは目を丸くしてゴン之助を見つめます。 「助けに行くと言っても、一体どうやって…?」 ゴン之助は胸をそらして空を見上げました。 「さいわい、今はたそがれの時。黄昏は猫族の時間だ。夕焼けの魔法が力を貸してくれる」 そう言うと、ゴン之助はお日さまの沈んでいく方角にひらりと顔を向けました。 雲の隙間から流れ込む夕陽に照らされて、ゴン之助の金色の瞳と毛並みが、夕焼け色に染まります。 全身の毛を逆立て、頭から肩、腰、そして尻尾の先まで、ゴン之助はブルブルッと震わせました。 すると……二人の回りから、ふっと、街のざわめきが遠ざかってゆきます。 「さあ、トードリ!」 ゴン之助は軽やかに、ギンコウの玄関に向かって駆け出しました。 トードリも慌ててその後を追います。 「まて、ゴン之助、シャッターが閉まっておるぞ!」 トードリがそう叫んだのと同時に、ゴン之助の身体はするりとシャッターを通り抜け、銀行の中に消えてゆきました。 「こりゃあ、幽霊顔負けじゃ」 トードリは肩をすくめ、頭に乗せたソフト帽をかぶり直してから、ステッキをついてやはりふわっとシャッターを通り抜けました。 広々した銀行の中には幾人かの人間達が残っていて、それぞれ机に向かいながら何やらせっせと仕事をしています。 ゴン之助はその間を通って、もうずっと奥の方まで走っていました。 「これ、ゴン之助、年寄りを置いて行くもんじゃない」 「トードリ、あんたは幽霊なんだから、もう年寄りじゃないだろ」 「まあ……それもそうじゃな」 トードリはステッキをつきながら急ぎ足でゴン之助の後を追いました。 そして二人は並んで、奥の部屋へと進んでゆきます。 居残って仕事をしている人間たちは一人も、彼らに気付くことはありません。 「トードリ、『気持ち』たちが閉じこめられているのはどこだ?」 「一番奥の、大金庫の中じゃ」 今度はトードリが先に立って、コンクリートの壁をすり抜け、長く薄暗い廊下を進んで、ゴン之助を大金庫へと案内しました。 「まるでワシら、銀行強盗じゃな」 トードリは可笑しそうに微笑みながら、大金庫の扉を見上げました。 大きなハンドルのついた金属製の分厚い扉に、鍵がかかっています。 「……もっとも、幽霊には金庫破りの必要もないがの」 トードリはそう言って、すたすたと金庫の扉に近付きました。 そしていつも通り、その扉をするりと抜けようとしました。 けれどその時、トードリの身体はギュッと何かにぶつかったように、押し返されてしまったのです。 「こりゃどうしたわけじゃ。幽霊も通り抜けられないなんて…」 ゴン之助も金庫の扉をすり抜けようとしました。 でも、同じように何かに押し返されてしまいます。 「夕焼けの魔法でもダメだ…」 二人は顔を見合わせました。 ゴン之助は耳をピクピクさせて、もう一度金庫の扉を見上げました。 「……きっと、あんまり長いこと『気持ち』が置き去りにされたから、オカネが『気持ち』を閉じこめる力が、強くなりすぎたんだ」 「なんということじゃ!お金は想いを乗せて運ぶものなのに、それを閉じこめてしまうとは……」 ゴン之助はブルッと身体を震わせて、足を踏ん張りました。 「このままじゃ、『気持ち』もオカネも可哀想だ」 「どうする?」 「……『気持ち』の力を呼び戻して、ここから出してやろう」 「『気持ち』の力を、呼び戻す…?」 ゴン之助は頭を低くして、金庫に挑みかかるようにフーッと一声啼きました。 そして今度は背筋を一杯にそらしてから、声高く啼きます。 ……ニャーオー、ウニャニャニャニャ、ニャーオー…… ゴン之助の啼き声が風になって、遠く、街の中へ響いてゆきます。 「思い出せ!大切な『気持ち』を!」 銀行に居残って仕事をしていた人達の心に、ふっと風が吹き込みました。 そのうちの一人は、今日、銀行にお金を預けに来たお婆さんのことを思い出しました。 お婆さんは、息子がお小遣いだとくれたお金を大切そうに抱えてやって来て、いつかその息子のために役立てようと、自分では使わずに銀行に預けていったのです。 大金庫の扉の前で、ゴン之助は再び叫びます。 「思い出せ、ありがとうの気持ち!」 すると街ゆく人々の心にも、柔らかな風が吹き込みました。 一人のさらりーまんは、仕事で付き合いのあるお客さんの顔を、急に思い出しました。 今ごろどうしてるかな、元気にしてるかな?と、わけもなく暖かい気持ちがわいてきます。 ゴン之助は更に叫びます。 「思い出せ、ご苦労様の気持ち、おめでとうの気持ち、お大事にの気持ち、よろしくどうぞの気持ち……!」 駅へと道を急いでいた別の一人は、子供たちの顔が急に浮かんできて、そうだ、ケーキを買っていこう、と、遠回りして帰ることにしました。 ゴン之助は力いっぱいに足を踏ん張り、ひときわ高く叫びます。 「思い出すんだ!大好きだよの気持ち……!」 トードリはゴン之助の隣で、目を大きく見開き、ふるえる両手でステッキを握りしめます。 街を過ぎゆく人々の心に、ふわりふわりと風が吹き込み、それぞれの思いを呼び覚ましてゆきます。 ご苦労様の気持ち、おめでとうの気持ち、お大事にの気持ち、よろしくどうぞの気持ち、大好きだよの気持ち、そして、ありがとうの気持ち…。 「ややっ、ゴン之助、金庫が…」 トードリが驚いて声を上げました。 金庫の扉が、虹のように七色に輝き始めたのです。 「大切な『気持ち』が、よみがえるっ」 ゴン之助はぐっと尻尾を持ち上げて、そう呟きました。 ゆらゆらと虹の光に包まれた金庫の扉から、やがて、一つ、また一つと、透き通った光の玉が飛び出してきました。 次々に飛び出してくる光の玉は、七色に輝きを変えながら、シャラシャラと音をさせてゴン之助とトードリの回りを飛んでいます。 二人はその透明な、美しい光の渦にまかれながら、もう何も言えずに立ち尽くしておりました。 「トードリ…」 「ゴン之助…」 すると急に、数え切れない程の光の玉が廊下の向こうへと流れ始めました。 ゴン之助とトードリも、光の後を追って走ります。 虹色に輝く光は、銀行の廊下を明るく照らしながら通り抜け、広々とした部屋を抜けて、壁をすり抜け、ついに道路へと飛び出しました。 そしてもう一度大きな渦になってクルクル回ったかと思うと、それから急にスピードを増し、街中に広がってゆきました。 銀行で居残り仕事をしていた人達も一人残らず、不思議な光が部屋を駆け抜けてゆくのを見ました。 道を歩いていた人も、自動車に乗っていた人も、誰もが皆、夕暮れの街を虹色の光が駆け抜けてゆくのを目にしました。 光の後を追って銀行から出てきたゴン之助とトードリは、柔らかな光が街を包み、夕焼け色の空に光が消えてゆくまで、じいっと見つめていました。 やがてゴン之助は、もといた階段の隅に立って、静かに呟きました。 「それぞれのあるべき場所に、『気持ち』たちが帰っていったんだ…」 トードリもその隣で、ステッキを握りしめて立っています。 「うむ…」 いつの間にか道路には街灯がともされ、銀色の光の粒子が道行く人々に降り注いでいました。 自動車はヘッドライトをつけて、光の帯を残しながら走りすぎてゆきます。 空には、生まれたばかりの細い月が、仄白い微笑のように浮かんでいます。 その月を淡い虹色の光のレースが、ゆったりととりまいています。 「…ワシも、ワシのいるべき場所に帰るとするか」 ゴン之助はトードリを振り返りました。 トードリの姿はもう、半分透明になっていました。 「トードリ、おれもギンコウが大好きになったぞ。たとえオカネが『気持ち』を閉じこめてしまっても、『気持ち』がよみがえるのは、やっぱりギンコウからだ」 トードリはニコニコして、指先で髭を撫でました。 「ありがとう、ゴン之助…」 そう言うとトードリは、半分透明になった手で、やっぱり透けて向こう側の見えるポケットから、バラ色に輝くオカネを取り出してゴン之助の前に置きました。 その透明にきらきら光るオカネをゴン之助がそっとくわえると、それは美味しそうな魚の頭に姿を変えました。 ゴン之助はその魚の頭を、ちょこんと自分の足もとに置いて、トードリを見上げました。 「…さよなら、トードリ。元気で」 そして足もとに置いた魚の頭をもう一度くわえて、そっとトードリの方へと差し出します。 トードリが笑って魚の頭を受け取ると、それはたちまち、大きなバラ色のこうもり傘に変わりました。 トードリはそのこうもり傘をパッと開きました。 柔らかな夜風を孕んで、バラ色のこうもり傘は空高くトードリを運びあげてゆきました。 ゴン之助は、トードリの姿が夜空の星の間に消えて見えなくなるまで、じっと見送っておりました。 トードリが見えなくなっても、星々は微かな瞬きを、ゴン之助とこの街に降り注ぎ続けます。 冷たい夜の風が、ゴン之助の毛並みをさあっと撫でて渡ってゆきました。 ゴン之助はブルッと身震いして立ち上がりました。 見ると、ゴン之助の足もとには、魚の頭がそのままに、美味しそうな匂いをさせてちょこんと座っておりました。 ゴン之助はそれをくわえると、住み慣れた街の宵闇の中に、足音もなく消えていったのです。 |
| (おわり) |
| 『楽園』さんに登録しました。 「らら美」などで検索すると、 拙作に投票できます。 |
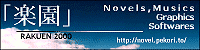 |