(ときじくのはな)
1 和服に身を包むとき萠香は、自然と背筋が伸び、気分が引き締まるのを感じる一方で、肌を滑る絹の感触に、どこかしっとりと濡れた艶めかしさを、嗅ぎとることがあった。 素肌に触れる絹の風合いは、意識の古層を掘り起こす。それも単に一人自分の体験を遡るのではない。絹と人との幾世代もの睦み合いが、直に肌身に感ぜられてしまう瞬間があるのだ。人が絹を紡ぎはじめたはるかな昔へと、皮膚感覚が道を拓く。 一反の着物地を作るのには、およそ十三枷の絹糸が必要だと言われている。それは実に、二千六百粒もの蚕蛾の繭から紡がれる糸の量だ。一枚の着物には、それだけの数の命が懸かっているのだ。 にも拘らず、奪った命の生々しさは、衣鳴りの緲かな息遣いの他には、一切の痕跡を残さない。秘めて、秘めて、秘め抜いた命の息遣いは、どんな植物よりも植物めいた静けさ、やわやわと滑らかな絹の風合いに変容する。ちょうど、木綿の綿[ワタ]と同じ音を持ちながら、繭から作られた真綿の方こそが真の綿と名乗るように、絹は、動物から植物へと存在を越境するような不思議を秘めている。 萠香は草木染めの着物を好んだ。動物的な命の煌めきを秘した絹の地に、植物の<血潮>が色を添える−−そんな転倒を含んだ空想が、萠香を眩惑した。動物と植物、二種類の存在が境界を曖昧にする、その間[あわい]に、絹を纏う萠香自身、いつしか肌合いから溶け込んでいくような気がするのだった。 だから和服に身を包むとき、人の手がまだ萠香に触れぬ先から、存在の睦み合いは始まっている。素肌を隠すとき、或いは、隠した素肌を再びさらけ出すとき、絹は緲かな息遣いで、密やかに萠香を愛撫する。 絹を身に纏うことは、裸体を曝す以上の官能を含んでいるのではないか……萠香は漠然と、そんな感覚を持っていた。それは孝彦と出会う前から感じていたことだし、彼を失った今でも、変わってはいない。 長襦袢を着ただけの自分を鏡に映しながら、萠香はふっと、孝彦のことを思った。 孝彦の前で初めてこの姿になったとき、彼はどんな眸をしていたろうか。波の模様を地紋に織り出した、軽い紋綸子の襦袢には、一面に、真っ紅な蝶の柄が染め抜いてある。孝彦の眸には一瞬、血飛沫を浴びた女のように見えたかも知れない……今にして萠香はそう思う。 あの夜、彼女が帯を解き、着物を脱いで長襦袢一枚になったとき、ホテルのソファに身を沈めていた孝彦は、確かに萠香を見上げ、一面に舞う真紅の蝶を見つめたはずだ。そして孝彦の眸には、必ず何かしら激しい、深みから来る動揺があったのに違いないが……萠香にはあの時の孝彦の表情が思い出せない。彼の眸に宿っていたのは、哀しみか、憎しみか、憧憬だったのか。 非存在の蝶−−孝彦はそう言った。己の救われなさを知り抜いた彼の、それは告白なのだと、萠香は思った。 あの夜、孝彦は萠香に語った。 「萠香サンは、まだ知らないんだよね……」 告白……それとも懺悔。 それとも、もっと暗い衝動に駆られた底深い悪意か、或いは、孝彦自身にもどうすることも出来ない、従うほかに術のない、絶対的な命令でもあったのか。 今ではもう、萠香には分かりようがなかった。あの夜の孝彦が何を考えていたのか。どんな表情をしていたのか。それどころか、あの一夜を共に過したのが本当に孝彦だったのか、或いは何かもっと別の存在だったのかすら、萠香にはもう分からなくなっていた。 さまよう思考とは裏腹に、萠香の手は無駄のない動きで衣桁屏風から着物を外していた。障子越しの冬の陽射しが、やわらかに絹のおもてを照らし出していた。 孝彦と萠香を最初に結びつけたのが、この着物だった。正確には、着物だけでなく襦袢や帯や小物まで含めた「装い」の全体が、二人を呼び合わせ、出逢わせたのだ。 淡い萌葱色の縮緬に、裾には一輪の装飾的な花が描かれている。その花弁が高く吹き上げられたかのように、袖口から袂へと、幾片かの花弁が舞い掛かる。実在の花の中では、たぶん罌粟の花に一番近いのだろう。大振りの花弁が、長く伸びた茎の先にひろがるその紅い花は、モダンな印象にデザイン化されていて、着物の柄としてはあまり季節を選ばない。 それは萠香にとって、特別な意味のある柄だった。風に戯れる一輪の紅い花。 長襦袢の上にその着物を羽織る瞬間、萠香はいつも、自分を包む空気が変容するのを感じた。その着物に袖を通すことは、彼女にとって一つの秘儀でさえあった。色褪せていた事物が鮮やかさを取り戻し、遠いスクリーンの向こうにあった世界が、眼前で息を吹き返す。触れれば押し返してくる手応え、活き活きとした現実感が、この着物に袖を通した瞬間、萠香のものになるのだ。死んでいた魂の半分を呼び戻す、それは神秘な降霊の儀式だった。 萠香は縮緬の着物を羽織って鏡台の前に立ち、そっと両手を広げた。 袂に降りかかる幾片もの紅い花弁。裾にただ一輪咲き綻び、細い茎の先で風に揺れる、潤んだような艶を含む紅い、紅い花。 非時の花−−孝彦はそう呼んでいた。 萠香の頬には、いつしか一筋の滴が零れていた。その着物に袖を通した今、萠香は、ようやくはっきりと確信することが出来た。孝彦の死に、責任を感じる必要はない。ないのだ。同情を寄せる必要すらも。 非時の花は、いつかきっと、非存在の蝶に変化するのだから。 2 視界の端で、真っ紅な花弁がふわりと風を孕み、一片、二片、まるで意志を持つもののように、退いては戻り、ゆるゆると旋回しながら舞っていた。 無論、現の花である筈はなかった。 それは萠香には馴染みの、心地よい幻視だった。時間の諸相が息を潜める瞬間。時も処も選ばず日常の中に滑り込んでくる、不可解に鮮烈な、幻視。 が、それも束の間、目を向けて捉えようとすれば忽ち、幻の花は視界から失せる。 萠香はその日何度目のことか、消えた幻を追うように視線を彷徨わせていた。 私鉄線の始発駅だった。 萠香はプラットフォームの中ほどで、次の電車を待っているところだった。 そんなとき不意に、横合いから声が聞こえた。 「あっれー、図書館のオネーさんだ」 不躾に侵入してきた声に、萠香は仕方なさそうに目を向けた。ひょろりと背の高い男が派手なスーツに身を包み、いかにもという感じの丸眼鏡を鼻先に乗せている。 「あ……椙田……さん?」 男は愛想を振りまきながら萠香に歩み寄る。 「そうそう、椙田です。覚えててくれたんだ。えーと……そう、萠香サン、だったよね」 妙なことになったな、と萠香は思った。椙田は、勤め先の図書館でちょっと顔見知りになっただけの来館者だ。自称、フリーのアート・ディレクターだとかで、何度か資料探しの相談を受けたことがある。一緒に電車に乗ることになっても、話題が続きそうにない。 しかし椙田は無遠慮に隣に来て、軽い早口で喋り始めた。 「なに、着物なんか着ちゃって、いや、似合ってるけど。あれ、お茶のお稽古とか?」 「ええ……まあ……」 萠香と歳はいくらも違わないか、もしかすると年上だったかも知れないくらいなのに、喋り方は完全に別世界の人間のようだった。普段縁のないタイプなだけに、萠香は戸惑いが顔に出るのを気にして視線をよけた。 と、何気なく椙田の後ろに目が行った。先刻から、ずっとそこに立っている人影があったのだ。真っ紅に染めた長髪が目をひく。萠香よりは幾つか年下だろう、だぶだぶのパーカーとジーンズを着てポケットに両手を突っ込み、どこにも力が入っていないような格好で、じっと立っている。 「あ、こいつ、俺のオトモダチね」 言いながら、椙田はその若者の肩に手を掛けた。 「一緒にアトリエ借りてる、こいつもアーティストよ。孝彦っての。……で、萠香サンはね、T図書館の司書の人で、オキーフとかスタイケンとか、探してくれたのもこの人」 萠香はぎこちなく会釈したが、孝彦はまるで無関心のように、萠香の顔さえ見ずに黙ったままだった。 椙田はそんな孝彦の様子に、苦笑混じりで言い訳する。 「ちょっと、変った奴でね……」 ふわりと、風が孝彦の紅い前髪を揺らした。電車がホームに入ってきた。 萠香はそそくさと乗り込んで隅のシートに腰掛けたが、案の定、椙田が隣に座る。孝彦の方は車両の連結部分にもたれかかるようにして、それでも一応、二人の前に突っ立った。 やがて電車が動き出し、しばらくの間は椙田が一人で喋っていた。多少鬱陶しいとは思いつつも、萠香は適当に相槌を打っていた。申し分の無かった一日に、この程度のことは我慢しようと思った。さらりと乾いた秋の空気は涼しく、適度に雲が出て陽射しを和らげてくれるので、帯付きで出歩くには最高の気候だった。萠香にとっては特別な意味のある装いも、非の打ち所なく綺麗に着付けられた。何のトラブルもない一日。あとは家に帰ってゆっくりとバスタブで手足を伸ばせば、それで何もかも満足な一日が仕上がる。日常が要求してくる事柄を手際よく片付けながら、視界の端に舞い掛かる花弁の幻視を楽しんでいられる、申し分のない平穏な一日。 ふと視線を感じて、萠香は目を上げた。孝彦が、じっと彼女の方を見ていた。正確には、彼女の着物の袂のあたりを見つめている。その視線が、ゆっくりと裾の方に下りていくと、青年の口元に、幽かな笑みが浮かんだ。 何だろう……と萠香が不審に思っていると、唐突に、孝彦の視線が真っ直ぐ彼女に向いた。 ちょうど椙田のお喋りが途切れたときだった。孝彦は薄い笑いを口元に浮かべ、パーカーのポケットから一枚の紙片を取り出した。 「これ、あなたにあげるよ」 萠香の目の前に突き出されたのは、モノクロで印刷された、何かのチケットだった。乱雑な写真のコラージュを背景に、見慣れない横文字のタイトルが踊っている。 膝の上でバッグを持ったまま、萠香はすぐにはチケットを受け取ろうとはしなかった。 椙田が如才なく口を挟む。 「cursus doloris――ラテン語だよ。こいつが付けたタイトル。仲間たち何人かと、場所借りて展覧会やるんだ。確か……『哀しみの航路』っていう意味……だよな? 俺なんかと違って、孝彦って、けっこう学があるんだ」 椙田の言葉など耳に入っていない素振りで、孝彦はごく自然な動作で萠香の片手を取り、チケットを持たせた。 「来てください」 「え、でも……」 萠香が戸惑っているのを見て、ほんの一瞬、孝彦は口を噤んだ。 だが、すぐにもとの薄い笑みを浮かべ、呟く。 「……たぶん、そうだと思うんだ。あなたも、そうなんだろうってね」 そう言って、孝彦は目を伏せた。 「何のこと……?」 孝彦は俯いたまま、幽かに笑った。その笑い方が、不思議と幸福そうに見えた。 萠香はすっかりわけが分からなくなり、孝彦を見つめていた。孝彦はするりと両手を吊革に掛け、萠香を見下ろして微笑む。無邪気な笑顔だった。 「あなたに、見て欲しいのがあるんだ……見せてみたい、って言う方がいいのかな」 「なんで……」 電車が減速を始めていた。次の駅のホームが、窓の外に見えた。 孝彦はゆっくりと、萠香の足下に視線を落とした。 着物の裾に咲く、紅い花を見つめているのが分かった。 彼は、口の中で何かを呟いた。 「え……?」 聞き返した萠香に、孝彦は小さく笑って首を振る。 「……来れば、分かるよ」 それだけ言うと、孝彦は人の間をすり抜け、ドアの方へと歩いて行ってしまった。椙田も「それじゃあ」と言って、席を立つ。 電車が止まり、ドアが開いた。 孝彦はゆったりと身体を揺らしながら、ホームへと降りて行った。椙田だけが一度振り返り、萠香に手を振って見せた。 ……非時の花。 孝彦の呟きは、萠香の耳に、そんな風に聞こえた。 3 次の週の土曜日、何故その駅で降りてみる気になったのか、萠香自身にも分からなかった。 お茶の稽古の帰りにいつも使っている路線の、途中駅だった。 萠香は手にしたモノクロのチケットに目をやった。 cursus doloris――哀しみの航路。その下に小さな字で、<5th Labo>という会場名が書いてある。 場所は既に、情報雑誌で調べてきた。いわゆる、若者が多く集まる街の、幾つもある小さな貸しスペースの一つらしい。 紅花染めの紬にレースのショールを肩に掛け、萠香は夕暮れかけた駅前の広場を横切った。どんよりとした曇り空の下、大勢の若者たちが花壇の縁に腰掛けたり、ファーストフード店の前でたむろしたりしていた。 場違いな和装の萠香を珍しそうに眺める者もいたが、萠香は不躾な視線を気にも留めなかった。もともと、外側で起こる出来事にはあまり関心が向かない質で、無関係の他人が自分をどう思うかには、さほど興味がない。他人にも、外界にも、自分から働きかけようなどとは金輪際思いもしないのが、身に付いた生き方だった。 ただ風に吹かれていればいい。……紅い花のように。 自分の閉鎖的な性格をよく自覚している萠香には、だから、この日の行動は我ながら意外なものとしか言いようがなかった。何かに引き寄せられているような気がするのは、意志的な行動を嫌う普段の傾向から来る、心理的な言い訳なのだろうか。 馴れた足裁きで裾を蹴る度に、八掛けの藤色が足下に咲く。 萠香は心の中で繰り返していた。 非時の花…… あの青年が呟いた言葉が、なぜか気になって忘れられない。 『非時の香菓』という言葉になら聞き覚えがあった。古代神話で、多遅摩毛理が常世の国へ行き、持ち帰ったという不老不死の果実だ。しかし彼が戻ったとき、不死の果実を捧げるべき垂仁天皇は既に亡く、多遅摩毛理は御陵の前で慟哭して、命果てたという。 似たような話は世界中にある。例えば、秦の始皇帝が徐福に命じた不老不死の薬探し。徐福は東方の海の彼方、十五匹の大亀に支えられ、神仙が棲むという、蓬莱、方丈、瀛州の三神山へ向かい、不老不死の神薬を求めた。徐福は三神山には至らず、倭国日本に来て死んだという伝説もある。新宮市蓬莱山には、徐福のものと伝えられる墓があるという。 オデュッセウスがオギュギア島に七年間留まる間、アトラスの娘カリュプソーは彼を不老不死にしようと試みたが、成功することはなかった。他方、エンデュミオンは月の女神セレネーに愛されて不老不死となり、けれど永遠に、眠り続ける。浦島太郎にしても、竜宮に至り不老の歓楽を貪るが、その代価は高くつくことになる。 人の身に永遠は向かないのだろう、と萠香は思った。だからこそ皇帝や大王は、人の身ならぬ不死を必要とするのかも知れない。 非時という言葉は、永遠を指すのだろうか……。だとしたら、時間の永続ではなく、時間の否定こそが永遠を意味するということなのだろうか。 視界の端に、紅い花弁が舞っていた。花弁はまるで蝶のように、舞い上がり、旋回して、風の中に消えた。 駅前の大通りを抜けて、交通量の多い二車線道路へと折れて少し行ったところに、そのビルはあった。 何の変哲もない四角い建物で、吹き付けの白い壁は、排気ガスで全体が黒ずんでいた。ビルの右端に地下へと降りる階段があり、その入り口に、銅板に飾り文字で<5th Labo>と打ち出した小さな看板が出ていた。 階段を下りたところに分厚いオーク材の扉があり、同じような銅の看板が打ち付けてあった。看板の下には、チケットと同じデザインのチラシが貼ってある。 萠香は力を込めて、扉を引いた。 入り口のすぐ前で、背の高いオブジェが視界を塞いでいた。スチールワイヤーで出来た二つの人体が、攻め合うように絡みついている。天井からは薄い白布が何枚もふわりと床まで降りていて、店内を幾つかのブロックに仕切っているのが分かった。微妙な色彩の間接照明が布を照らし出し、空調の風が布を揺らす場所では、不思議な雲の流れのように錯覚しそうだった。 オブジェの所が受付になっていた。萠香はチケットを見せ、会場の中へと足を踏み入れた。 中へ入って分かったのは、入り口で見たときに間接照明だと思った明りが、実際には、ヴィデオ映像を流しているディスプレイの光だだったことだ。あちこちに投げ出されたような格好で置かれたディスプレイは、見知らぬ風景や、断片的な人の表情や、単純な幾何学図形を映し出していた。 会場にはそこそこ人が入っていたが、何となく得体の知れない感じのする服装が多かった。主催している連中の人脈が知れるように思えた。 壁には抽象的なアクリル画やモノクロの写真が掛けられたり、額縁の上からペンキをぶちまけたような作品や、新聞紙とトイレットペーパーを立体的に張り付けた一角もあった。 萠香にはこの種の「アート」は理解できなかった。奇を衒っているだけなのか、オリジナリティがあるのか、そういう区別が付かないのだ。 それでも、会場に並ぶ作品を見る限り、本当に独自の世界を持っていると思えるものは、殆どないような気がした。どこか借り物の感性が匂うのだ。そのせいか、理解されることを放棄したような分かり難さのわりに、世界や他者を拒否する仕方が、いかにも中途半端な印象を与えるのだった。如何に奇妙に見えようとも、「それ」を表現せずにはいられない止むに止まれぬ衝動でも伝わってくれば、少しは心も動かされるのかも知れないが……と、萠香は思った。 こんなものを見るために、自分はここに来たのだろうか。そう考えると、萠香は肩のあたりに重苦しい疲れを感じた。 こんな場所からはさっさと引き上げよう。萠香は色彩々に髪を染めた連中の間を通り抜け、白布で仕切られた反対側へ出た。 光の感じが、変った。 青っぽい光が、天井と足もとを照らしている。光源が直接目に入らないよう、壁際のライトには覆いがしてあった。幽かに、伽羅を焚く香りが漂い、遠い海鳴りのようなざわめきが、どこからか聞こえてくる。 壁際に、一枚のパネルが掛けてあった。 萠香は吸い寄せられるように、そのパネルに近づき、立ち尽くした。 両手を広げたくらいの大きなパネルには、ある光景が、写し撮られていた。 写真とも絵ともつかぬ、妙な質感の画面だった。絵のような写真とも思えるし、写真のような絵にも見える。 画面の下方には草原が拡がっていた。茂る草は灰色を帯び、強い風が吹き抜ける草原は、海に臨んで切立った崖となり、果てている。その向こうでは、白い波頭の間に間に黒々と凍える海が、底深い不可知を湛えて悠然としている。空には厚い雲がたちこめ、僅かに漏れる陽射しは、弱々しく中空を照らすだけだ。 冬の海。人の侵入を拒む権威を秘めた、言知れぬ深み。 しかし、萠香の視線は、その画面の中心にあるものに、釘付けになっていた。 海に臨む崖の端近く、草原の果てる丁度そのあたりに、濃い緑の草が一本、細い茎を空へと伸ばしている。しかし、その先端に咲いている筈の花が、無い。 代わりに、花が咲いていた筈の草の先からは、飛び立ったばかりの紅い蝶が、ひらりと、海の方へと舞い上がっていく姿があるのだった。 沈んだ色調の空と海と草原とを背景に、その紅い蝶だけが、血溜りのように濃く、潤んだような艶めかしさに濡れていた。 萠香は腕のあたりにさぁっと鳥肌が立つのを感じた。 蝶に変化する花…… 紅い…… 「なんで、これが……」 口の中で呟きながら、萠香は必死に、挫けそうになる膝頭に力を込めていた。 萠香はあの蝶を知っていた。 蝶に変化する、紅い花を。 あの空も、海も、崖となって果てる草原に吹く強い風も。 けれどそれは、萠香の心の中にしか存在しない筈の光景だった。現実の体験や記憶とは関係のない、空想の世界と言ってしまえばそれまでの、一つの幻視。いつの頃からか心に棲みついて離れなくなった、強烈なイメージ。目を閉じているときだけに見えるわけではなかったけれど、生の視覚を通して、外側の世界にそれを見付けることなど、決してあり得ぬ筈の心象風景だった。 パネルの下には、小さな紙片に『非時の花』というタイトルが書かれていた。そして、『江上孝彦』という名前も。 「……あなたも、この花を知ってるんでしょう?」 真後ろで、彼の声がした。 萠香は背筋にぐっしょりと冷たい汗をかき、振り返った。紅い天鵞絨のシャツの上から三ツ釦の黒いジャケットをはおった孝彦が立っていた。 「……僕たち、魂の一部を共有してるんだ。そうでしょう?」 目を逸らすことさえも出来ずに、萠香は震える声で問い返した。 「あなた……誰なの?」 しかし孝彦はその問いには答えず、萠香の目の前で突然、会場の壁からパネルを下ろし始めた。 慌てて集まってきた仲間たちを後目に、孝彦はパネルを店の裏口の荷物置き場に持っていくと、無造作に放り出した。 「何のつもりだよ孝彦!」 駆けつけた椙田が孝彦の腕を掴んだ。孝彦は鼻先で笑った。 「もう、人に見せる必要が無くなったからさ。見せたい人は、来てくれたからね」 「でも客はまだまだ来るんだし……」 椙田の腕を振りほどいて、孝彦は萠香の所に戻り、彼女の肩に手を回した。そして椙田たちの方を振り返ると、孝彦は吐き捨てるように言った。 「嗅覚の無い奴に、匂いは分からない。芳香も悪臭も、そいつらにとってはもとから存在しないんだから!」 孝彦は萠香を抱きかかえるようにしてスタジオを出ると、階段を上り、人混みの中を歩き出した。 肩を抱かれて歩きながら、萠香は力の抜けそうになる足取りを、幾度も孝彦に支えられた。 あのパネルの前に立ったとき、自分の中にしか存在しない筈の心象風景と、はっきりと外界からもたらされた視覚情報とが、一つに重なっていた。内部と外部の境界が定まらなくなり、萠香は混乱していた。 非時の花。 蝶に変化するあの紅い花を、萠香はそういう名前で呼んだことはなかった。けれど、確かに、孝彦は自分と同じ幻視を共有している……萠香にはそれがどういうことなのか、理解できなかった。 同じ一つの内的なイメージを、別々の人間が抱いているなどということが、本当に有り得るのだろうか? 「今日は付き合ってくれるでしょう? ねぇ、ボク、あなたのこと何て呼べばいい?」 孝彦は無邪気そうに笑いながら、萠香を覗き込んでいた。 抵抗する意志も、力も、萠香にはなかった。 |
| 『楽園』さんに登録しました。 「らら美」などで検索すると、 拙作に投票できます。 |
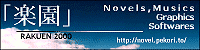 |