![]()
牡丹殿下[はくぼたんでんか]の仰るには、真の貴族的精神は現実を単なる事実の相において捉えることができないらしい。その類の精神は常に、事実の向こうに栄光を求め、現在の向こうに過去や未来や永遠を見出すのだと言う。 「そしてね、君……ここからが肝心なんだが……それゆえ真にロマンチックな恋愛を経験する勇気は、貴族的精神の持ち主だけの特権なんだよ」 殿下はそう言いおかれて紙巻き煙草をくゆらせた。金色の日が射し込む山小屋の中で、最新流行の格子縞の乗馬服に身を包みゆったりと安楽椅子に身を任せる白牡丹殿下の姿は、確かに事実の相で捉えられる以上の輝きを放っていた。冬の厳しさがたまさか忘られたような午下がりの光輪に包まれ、殿下の瞳は未だ出逢わぬ数々の思い出を遠く見霽かすように潤んでいる。殿下の眼差しのもとでは、冬日の幕間の一時の麗らも、天上の楽園の永遠の光栄も、しかと区別されることはないかのようだった。この小屋へ至る遠乗りの途中、殿下はこんな日和を遠い異国では『老婦人の夏』と呼ぶのだと仰った。人の身には沁みる言葉だね、と言い添えられて。 何処までも透明に冴え渡った空気に、時折、僅かな弛みが生じては、歌い初めたばかりの幼い鴬の啼き声が運ばれてくる。「ケキョ…ケキョケキョ…」と啼くばかりで、どうしても巧く歌えない。鴬には鴬の言いたいこともあろうのに、それが巧く伝えられず、じれてじれて、忙しく「ケキョケキョ」と啼いている。同行の年上の友人、司祭の忍冬[すいかずら]は黙って薔薇色の果実酒を口に運んでは時折微笑んだりしていたが、もう一人のやや年下の同行者は、殿下の言葉に疑問を差し挟んだ。 「どういうことです、殿下? 百姓たちは恋をしないということですか?」 白牡丹殿下はゆっくりと煙草の灰を床に落としてから、この年下の友人の顔を眺めた。鬼百合大尉の軍人らしい飾り気のない物言いも、見るからに頼もしげな体つきも、そして何より自分を実際以上に見せようとしたり重要人物だと思い込みたがったりしない率直な性質も、殿下の常のお気に入りだった。殿下はいつものちょっとからかうような目つきで大尉に笑みかけられた。 「そんなことは言ってないよ、大尉。もちろん農民も商人も恋をすることはあるだろう。でも、真にロマンチックな恋はできないんだ。言い換えるなら、恋愛を永遠の相にまで高めることは、平民の精神では不可能だ。厳然たる事実の要求を理想の力でもって克服するには、それ相応の勇気が必要だからね。そんな勇気を持てるのは、真に貴族的な精神……或いは、真の無産者の精神だけだろうね」 そこまで仰ってから、白牡丹殿下はからかうように鬼百合大尉の顔を見て笑った。 「大尉、もちろん私は結婚という、あの神聖にして実用の理に適った制度のことを話しているのではないよ。ましてや若者の情熱が陥りがちな独占欲とも関係なければ、これこそ生涯でただ一度の恋だとか、ただ一人の恋人だとか、そういった個人的な感情……よしんばそれを思い込みとまでは言わないにしてもだよ……そんなものとも違う話なんだ。真にロマンチックな恋愛は、個人的感情ではないんだ。そう……祭りで仮面劇を演じる者が、ひととき神々の精神に自らを明け渡すように、真の恋愛とは、いわば恋愛の元型とでも言うべきものの前に自らの全存在が消失することに他ならない。世に溢れる恋愛事の中に、多かれ少なかれ個人というちっぽけな観念を揺るがす力があるのは、真の恋愛の残響のおかげだ。真の恋愛、恋愛の元型においては、自分が恋愛の当事者であることも、相手がまさにその人であることも、偶然の配役として理解されるべきだ。そして慎ましく……我こそはと力んだりせず、むしろ自意識の鎖を解き放って配役に相応しくあろうとすることが、人間の使命でもあるだろう。本当に意味があるのは、ただ恋愛が、真の恋愛がそこに表現されているということ、そのものなんだから」 殿下はそこで口をつぐみ、短くなった煙草を暖炉に投げ込まれた。鬼百合大尉は首を捻り、途方に暮れた顔つきで忍冬師に助けを求める視線を送った。司祭はグラスを手の中で揺らしながら、白牡丹殿下と鬼百合大尉の顔を順に眺めた。 「大尉、殿下の仰る真の恋愛に一番近い世界で生きているのは、他ならぬあなたなんですよ。貴族の中でもあなたのような軍人の家系は、血の中に揺るぎない恋愛の記憶を宿しているのですから。軍隊はこの世でもっとも恋愛に近い組織です。軍人は力と名誉に恋する人々です。一つの理想のもとに、己を無にするまで没入することにもっとも長けた血筋とは、軍人の血筋に違いないのです」 「しかしその……」鬼百合大尉は腕を組んだまま呟いた。「軍人の血筋が恋愛に近しいというのは、どうも殿下がはじめに仰ったことと矛盾するように思うのですが。我々軍人は、物事を紛れもない事実の相において捉える人種なのですから」 白牡丹殿下は咲きこぼれるように微笑され、ゆっくりと首をお振りになった。 「それは違うな、大尉。軍人は物事を信念と理想によって捉えるんだ。事実の相において現実を捉えるのは、むしろ農民たちだよ。彼らは豊作の年には喜び、不作の年には哀しむ。疫病の猛威に曝されながら死者を見送り、祭りの日には歌い踊る。……彼らはそういったことども総てを、ただありのままに受け入れ、堪え忍び、自分の身にかかる不幸や災難をさえも笑う。決して運命に何故と問うたりはしない。ただ事実を受け入れ、淡々と日々をやり過ごす知恵を身につけている。……軍人ならば相手を敵と味方に分けて考える。或いは敵と味方とにかかわらず誇り高き武将か、そうでないか、と。だが農民は違う。見知らぬ相手は、ただの見知らぬ誰かだ。どんな相手であろうと、目の前に飛んできた藁屑と違わない。渇いているなら水を、飢えているなら麺麭屑を与えるかもしれない。剣を振りかざしているなら逃げるだろう。それだけのことだ。それ以上なにもない。見たままに応じる。それが農民の知恵というものだよ」 鬼百合大尉は相変わらず腕を組んだままだったが、今は物思う目になり、幾度か小さく頷いて殿下の言葉に耳を傾けていた。 「世界を事実の相において理解するのが農民の精神だというところまでは、少し分かってきたような気がします。その精神なくしては、この世は建ち行かないことでしょう。喜びの年も哀しみの年も種を播き続ける者達の精神は、確かに深い知恵に溢れていましょう。……けれど、そんな彼らの精神では、真の恋愛は出来ないと?」 「そこだよ、君!」白牡丹殿下は安楽椅子の肘掛けからちょっと手を挙げて見せた。「本当のところ恋愛とは、事実の相における出来事ではないのだよ! 事実のみを問題とするなら、恋愛は少しも現実的ではない。どうして一人の乙女が、一人の男にとって、それ以外の総ての人々と較べることもできないほどに貴重だなどということが起こり得るだろう? 恋愛においてはそんな状況が起こる。しかも相手をまだ良く知りもしないうちから! 純粋に事実の問題として考えるなら、これはまったく現実的ではない」 「それでは、恋愛は浅はかな夢幻、単なる感情の巧妙な偽りということになるのでしょうか?」 本気でそう考えているわけではなく、ただ殿下との会話の呼吸から、鬼百合大尉はそう反問した。殿下はお気に入りの友人の問いに、愉快そうに微笑まれた。 「大尉、もし君の言ったことが真実だったとして、それを私が知っていたとしても、そんな真実、私は世のために口を塞いでおくだろうね。しかし幸いなことには、恋愛は確かに現実のものだ。ただし事実としてではない。そして真にロマンチックな恋愛について言うなら、それは感情的なものですらない。人を取り巻く様々な事実の要求や、その人の内なる感情の必然をすら超えて、恋愛は現実化するのだよ」 鬼百合大尉は真っすぐに背筋を伸ばしたまま、ぐいと拳を握りしめた。 「けれど殿下、単純な言葉の論理によって、それは不可能な恋愛だと言わねばなりません」 殿下は柔らかな笑みで応えて、こう仰った。 「そうだよ、真実の恋愛は、およそ不可能な恋愛として現実化するんだ」 遠い眼差しは遥か高みの世界を映していたが、それはまた始まりの楽園のようでも、終わりの時の王国の来臨のようでもあった。匂わしげな殿下の頬には、伺い知れぬ謎を秘めた微笑が残る。 「一つ……恋にまつわる物語りでもして聞かせようか…」 そうして殿下は恋の物語を語られた。 |
台は……ここより遠からぬ地とだけ言っておこうか。時代も今から百年も昔のことと思ってくれたまえ。それよりも前か、それよりも後のことかも知れないけれど、とにかくまだ異国の侵入は無く、遠い過去からの記憶を抱いた風景がまるのまま残っていた時代のことだ。絵地図に描かれる世界の範囲は狭かったが、人々がその中で生きる世界の果ては、今よりも遥かに遠くへと広がっていた頃の話だ。 一人の乙女が父の領地から都にいる母の元へと呼び寄せられた。乙女の名は沙羅と呼ぶことにしようか。沙羅は幼い頃を両親とともに都で過ごし、父の帰郷について都を離れた。母君は根っからの都人だったため、由緒あり卑しからぬ土地とはいえ、田舎の暮らしに根を下ろすことは出来なかった。領主館を宮廷風の内装に改め、近隣の名士を呼び集めては舞踏会を催したりしたが、都の便りを聞くにつけ、母君の塞ぎの虫はいや増すばかりだった。結局二度目の冬を迎えることなく、母君は十になったばかりの沙羅と夫をおいて、都へと戻っていった。沙羅は十五の年まで父のもとで暮らし、十六の春に都の母のもとへと呼び寄せられることになる。 沙羅の父君は代々都の西方に豊かな領地を持っており、かつては宮廷でも重く用いられた古い貴族だった。その財産は王と並ぶ程だとも言われ、国中でも三指に入る豊かな家系だ。若い頃から都で学問を修めて教養に欠けるところはなく、身体は頑健、そして気難しく無口で厳格な父親だ。この父君も若い活力に溢れていた頃は、華やかな都の生活に魅了されもし、宮廷に咲く大輪の薔薇よと詩われた姫君の心を射止めんと、貴公子連中と恋の戦上手を競い合ったものだった。だが実際にその薔薇姫を手中に収め、子を成し、結婚生活が落ち着くにつれ、都の暮らしに満足ができなくなっていった。父君はまこと領地の丘に根を張る樫の老木、その枝先に萌える若葉のような方で、都には自分の根を張るべき大地がないことを知っていた。若さと引き換えに成熟を身に付けたとはいえ、体内に湧く活力は相変わらず人に勝るほどに溢れ、父君は世界の中心に立って周りを支配することの必要を日増しに感じていた。真っ直ぐな気性の本来の性向が、「汝、秩序の中心たれ」と声を大に要求するのだった。父君は身体中を駆け巡る本性の声に従い、領地へと退き隠ることを決めた。都では授からなかった男児の誕生をも、父君は故郷の大地の神秘な力に、密かに期待を寄せていた。まだ幼かった沙羅も、堂々と入領する馬上の父君の威厳、そしてその父君を迎える領民の期待に満ちた眼差しを覚えている。父君はまさに土地の秩序そのものであり、命の源を司る者であり、そして土地で生起する一切の事柄に無条件の責任を負うべき、ただ一人の人だった。父君は存分に腕を振るって領民を治めた。沙羅が成長するにつれ、西の領地はますます父君の色を映し、父君はますます土地の匂いを醸すようになっていった。殊に母君が都へと去ってからは、父君と土地とが含み合う様はとめどなく、明け暮れの山並みや草地の風さやぎ、そして村の粗末な軒飾りの一つに至るまで、父君の存在の刻印を映さぬものはないほどだった。父君は西の領地そのものであり、大地は父君のもう一つの姿だった。樫の木の丘から畑目の色具合を見渡し、稔りの行方に心を懸ける父君を見上げるにつけ、この父君がどうやって、この土地を離れあの夢幻のように華やいだ都で息をしていたものかと、沙羅は心底不思議を覚えるのだった。 沙羅にとって父君の領地での生活は常に素晴らしかった。父君が男児の誕生を諦め、母君が都へ戻ることを許してからは、沙羅は跡取り娘と見なされるようになり、西の大地にとって更に重要な存在となった。女相続人たるに相応しく、一流の教師が沙羅の教養を磨き、都人に負けぬ礼儀作法を身に付けさせた。母君は折々に訪ね来ては館に滞在したが、それは年中行事とも言うべき点景であって、西の大地の生活にとっては見慣れた客人以上のものではなかった。都に名を馳せる薔薇夫人たる母君も、そのことは重々承知していた。領主館に添えられた到来ものの薔薇として、母君は決して父娘の習慣を乱すことはせず、また娘の教育にも不満を述べ立てることはしなかった。それでも母君が運んでくる都の洗練は、それ自体が西の大地にとっての恵みの雨であり、薔薇夫人の滞在中、領地全体に新たな色が添えられるのだった。母君はいつも流行の服やら飾りもの、そして最新の話題を沙羅への土産に持ち帰ったが、これはいつか沙羅が宮廷に出るためには欠くべからざる準備でもあった。沙羅は母君の前でこそ都風の装いで身を飾ってみせたが、母君が去ると最新流行の服は衣装棚の奥へと忘れ去られた。沙羅は母から贈られた華やかな都の装いが、母の去った後の西の大地には相応しくないことを知っていた。薔薇夫人たる母が、ただその指先の一振りでもって領地中に魔法をかけている間だけ、西の大地は都の風を抱き留める。魔法が去れば、頼るべきは大地に張られた自らの根の他にない。沙羅は衣装棚から房飾り一つない、簡素な、けれど気の遠くなるほどの手間暇をかけて紡がれ織り出された高価な布地で出来た服を取り出し、安んじて袖を通すのだった。沙羅は乙女らしい華やかな夢よりも無骨な大地の現実を愛し、薔薇夫人はいとも華やかな魔法を、自らの存在によって世界に振り撒く。薔薇夫人と沙羅とは同じ種子からなる魅力を持っていたが、その花開く方向は正反対だった。母とその一人娘の間の愛情は、傍目にはやや他人行儀なほどに、距離をおいた自覚的なものだった。 沙羅はまた心から父君を尊敬し愛していたが、自分を見る父の表情に、時折、微かな落胆が潜んでいることを見逃しはしなかった。だがそれに気付いていると父君に悟らせるような素振りをするには、沙羅はあまりに誇り高い魂を持ちすぎていた。……私が男に生まれなかったことに何の咎があろう、私は凡庸な男子など及びもつかないほどに、立派な相続人として父の期待を越えてみせよう……そう、男子なら王の前には跪くばかりだけれど、私の前には王も跪くほどにしてみせよう…。実際、沙羅は申し分ない資質を日ごと年ごとに開花させ、誇り高い乙女へと生い立っていった。十五になるやならずの頃から、どんな話題にも自在に古典を引用しながら独特の考えを披露する知力と弁舌とを持ち、相手の心の些細な機微をも敏感に察して場を盛り立てる巧みを身に付けていた。音楽にも並々ならぬ才能を発揮し、笛でも琴でも扱いかねるものはなく、また歌声は厳格な父君の頬をも濡らすほどだった。馬を選ばせても相当の目利きで、もちろんちょっとした荒駒など苦もなく服従させる名騎手でもあった。父君もその家来たちも決して口には出さなかったが、これが男子の世継ぎであったならと、姫君の素晴らしい成長ぶり自体が、皮肉にも、叶わなかった希望の大きさを思い起こさせる小さな苦痛の種となるのだった。 十六の春、沙羅は西の大地を離れて都に上った。母君は数年来是非にと勧めておられたし、父君もそろそろ頃合と考えられ、充分な支度をさせて跡取り娘を送り出した。両親の思惑は沙羅にも充分わかっていた。望みうる最良の縁をつかみ、家系を存続させること。西の大地には領主の家系が守るべき伝統があり、召命があるのだから。しかし世間的に言われる如何なる良縁も、沙羅には不要なものに思えた。領主の家系の誇りを充分過ぎるほどに身に付けた沙羅は、この時既に、自己を自己自身において完結させるという、脅迫的な信念にとり憑かれていたのだ。結婚などという外的要因に頼ることなく己を完成してみせると、沙羅は固く心に決めていた。自分自身というものに外から何かを付け加えるなど、沙羅にとってはただぞっとするような想像でしかない。人生の計画図面の中に、他人の入り込む余地などあるとは思えないのだ。他人の助けを必要とするような欠損を、沙羅は自身の内に見出すことがなかった。人に与えることは惜しまぬ徳を持ちながら、人から与えられることには、沙羅はどうしても我慢がならなかった。家系とその召命を継承する義務については、最終的には養子を迎えることで解決が可能だということを沙羅は知っていた。貴族社会の中では珍しいことではない。子孫に恵まれぬ家が親類の二、三男を養子にするのは、ごく普通に行われている秩序の維持の一環だ。両親の希望に背くのは気の重いことだったが、結局義務を果たす意志の固いことに違いはないのだからと、沙羅は深いところでは楽観とも確信とも言える思いを抱いて都の門をくぐった。 |
| 『楽園』さんに登録しました。 「らら美」などで検索すると、 拙作に投票できます。 |
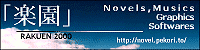 |